マレーシアでお米のおいしいお召し上がり方!?

こんにちは!たびなすびのちかです。
ペナンに来てから、米米うるさくてごめんなさい。米米言いすぎてカールスモーキーになりそうです。(ならない)
現在は、夫の親友坊主さんが持ってきてくれた山形産『つや姫』を食べているので、ノンストレス。これがいつか無くなる日が怖い…。
マレーシアにもジャポニカ米はある
ジャポニカ米は、日本とか韓国、中国など主に東アジアで食べられているお米で、タイ米のようなインディカ米に比べて短く丸っこいのが特徴。
マレーシアはインディカ米が基本なので、外食ではもちろんそれ。粘り気が全くなく、インド料理やマレー料理にはよく合います。
けど、和食には全くの不向き。これでおにぎりなんて夢のまた夢よ!
例えるなら、河原の石を一メートル積み上げなさいっ!そしたら終了っ!くらいの難しさ…。(わかりにくい)
でも、マレーシアには東アジア人もかなり住んでいるので、スーパーには一応売ってます、ジャポニカ米。SUMOとか、SAKURAとか、錦とか…。
絶対メイドインジャパンがつけなそうな名前で…。
SUMOはそれこそお相撲さんがご飯を食べているパッケージで、和食作るならこれよ!って感じでどこでも売ってるので、とりあえずこれを食べてました。
炊き方が悪いのか、水分量が足りないのかわかりませんが、まあこんなもんだよね⋯レベル。おにぎりはかなり難しいです、こっちのお米は基本的に粘り気が足りない。
日本人のために和訳がついてるんだけど…
他のジャポニカ米も試してみようということで、次に買ったのが、

SAKURA。
SUMOに比べると、パッケージが薄紫でサクラらしき花柄なので、ちょっと高級感漂います。(値段は同程度)
「パッケージ、素敵じゃん…」と思いつつ、おもむろに裏面を見ると、マレー語と英語と、日本語で書かれた、『お米のおいしい召し上がり方』
日本語、いる?
マレー語と英語はわかりますよ、いつもインディカ米を食べているマレーシア人や欧米人がなれないジャポニカ米を炊くんですから。
でもさ、人生数十年、食べたコメの量は数知れず…みたいな日本人に指南する必要があるんだろうか…。
日本語を読むのって日本人だけだしさ…。それなら北京語で全中華系を網羅したほうが良さそうだけど。なんてくだらないことをダラダラ考えながら、でも、どれどれ…と和訳を読み進めていったわけです。
秀逸の和訳にぐうの音も出ない
では日本語訳を見ていきましょう(マレー語と英語は省きます)
行程は、1〜5まであります。
1.1回洗います。
一回でいいの…。英語では “Rince the Rice ONCE” って大文字で一回を強調されてたから、皆、SAKURAの米は一回しか洗っちゃダメ…。
2.標準的には、お米の1.2倍の量です。お好みの水加減を決めてください。
日本のように、きっちりとした量を示すのではなく、自由に決めてね!って感じがいいね!
3.30分以上、水につけておいて下さい。
水に浸す作業も入れてるなんてしっかりしてるね!
4.こればかりは自動炊飯器におまかせ。
!!!!!
『こればかりは自動炊飯器におまかせ。』!?
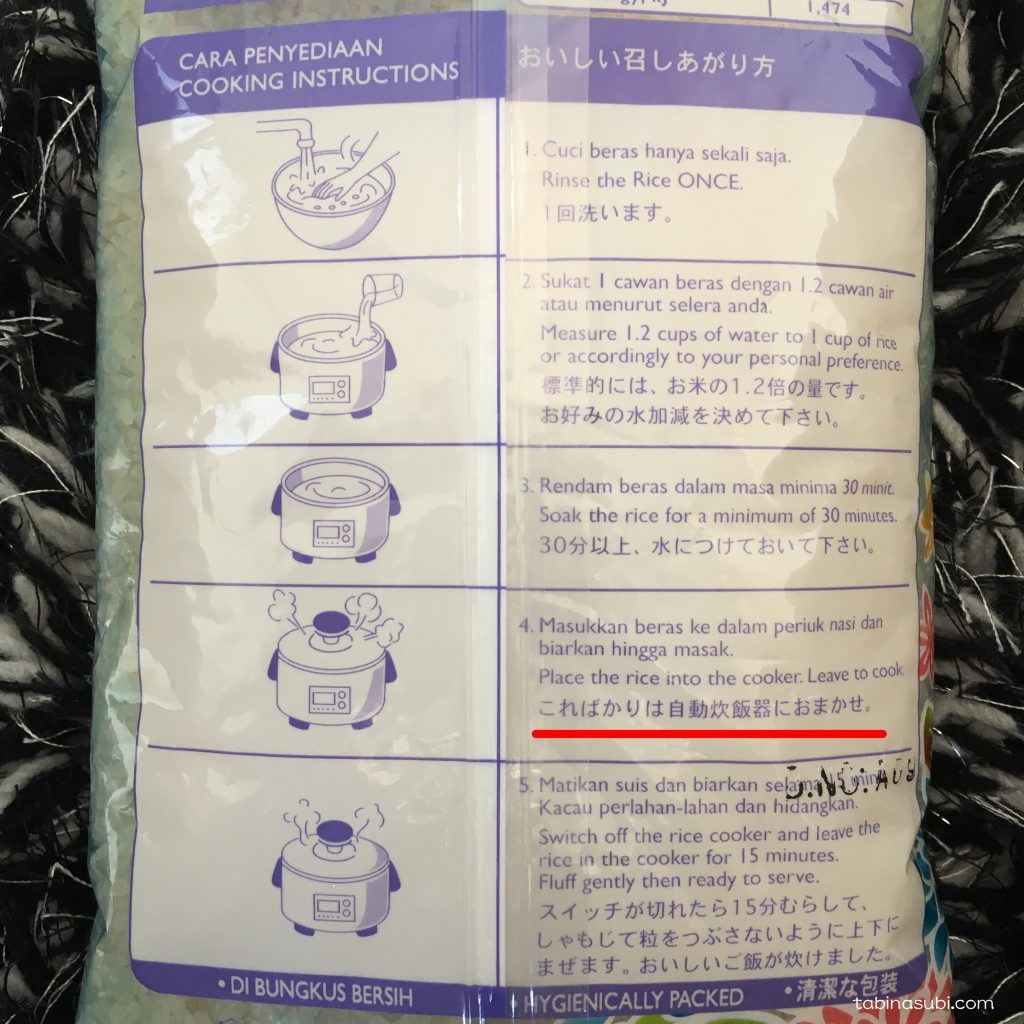
びっくりしすぎてリピートしちゃった…。炊くのは炊飯器にまかせなきゃダメなの…。
そう、その通り…。お願い…炊飯器さん…。
5.スイッチが切れたら15分むらして、しゃもじで粒を潰さないように上下に混ぜます。おいしいご飯が炊けました。
おいしいご飯が炊けましたーーー!炊飯器さんのおかげですーーー!
ネイティブチェックしても直すところがない
元日本語教師として、この和訳をネイティブチェックしてみましたが、直すところ、ないよね!野暮なことできないよ…。
だって、じゃあどうするの、「炊飯器で炊きあがるまで待ちましょう」とか?
うわー、センスない。自分で書いてて嫌になるわー。
「こればかりは自動炊飯器におまかせ!」に勝る日本語を思いつかないっ!
これ、英語だと、
Place the rice into the cooker. Leave to cook.
なのー。全然センスないー、日本語見習ってほしい。ということで、マレーシアでのお米に迷ったら、激しくSAKURAをオススメします!
味じゃなく!
最後まで読んでくださりありがとうございます。
📩 ご感想・メッセージ・ご質問等はこちらから 📩

ご訪問ありがとうございます、たびなすび(プロフィール)です。現在、マレーシアのペナン島を拠点に生活しています。このブログでは日常の小さな気づきや、心に残った旅の瞬間などをお届けしています。このブログが新たな冒険や発見のきっかけになれば嬉しいです。「住みたくなるようなお気に入りの街」を探す旅に出てみませんか?




